「コーヒー豆を冷やしたほうが、挽いた際に粒の大きさが安定して、おいしいコーヒーになる」という研究レポートを見つけました。
原文はこちら。
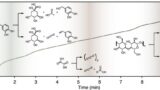
2016年の研究ですが、個人的に初耳でした。
記事要約
発表したのはバース大学の学生とコーヒーショップColonna&Small’sらのチーム。
コーヒーの産地・品種・加工方法が、粉砕時の粒度に影響するかを調査したが、特に影響はないことが分かった。
さらに、粉砕時の温度が粒度にどう影響するかを調べたところ、豆を冷やしたほうが、粒が小さく、粒度のばらつきが少なくなることが分かった。
実験方法は、マールクーニックEK43というミルで引いたコーヒー粉を、レーザー解析粒度分析にかけるというもの。
産地・品種・加工方法による比較
下記の4種類の豆について比較を行った。
| 生産国 | 品種 | 焙煎度 | 精製方法 |
|---|---|---|---|
| グァテマラ | カツーラ/ブルボン | シティ | ウォッシュド |
| エルサルバドル | パカマラ | アメリカン | ウォッシュド |
| タンザニア | レッドブルボン | アメリカン | ウォッシュド |
| エチオピア | 在来種 | シナモン | ナチュラル |
結果を現した図は以下。
1枚目の図では、粒子の大きさの分布(青)と、その積分値を使って全体のうちの割合を求めたもの(グレー。全体の99%が70μm以下であることを現している)
2,3枚目の図で、実線は粒子の直径、破線は粒子の表面積の分布。
黒、紫、赤、青はそれぞれタンザニア、エチオピア、エルサルバドル、グァテマラ。
(表面積のグラフは山が2つあるが、左は微粉、右がねらった大きさの粒子のもの。微粉が多く見えるが、これは横軸が対数目盛になっているため。)
この結果に対する研究チームの考察は
- 産地や加工方法の違いは、粉砕結果に大きな影響を与えない
- 今回の実験に使用したのはいずれも浅煎りの豆であったので、深煎り豆でどのような結果が出るかはさらなる実験が必要
温度による比較
上記のうち、グァテマラの豆を使って実験。
豆を紙コップに入れて蓋をし、液体窒素(-196℃)、ドライアイス(-79℃)、冷凍庫(-19℃)で2時間冷したものと、常温のもの(20℃)の計4パターンで検証。
表aはさきほどの検証と同様。実線は粒子の大きさ、破線は表面積の分布。
温度が低いほど、粒度のばらつきが小さいことが分かる。
表bは粒子の大きさの最頻値。温度が上がるほど大きい粒子になりやすいことを示している。
表cは分布の歪度(左右非対称性)。温度が低いほど左に偏った分布になっている。
表dは粒子の平均値。連続した形にはならず、-19℃から20℃へと温度が上がると、粒子の大きさの平均は小さくなる。
さらに常温に置いた豆と、-196℃に冷やしてから常温に戻した豆との比較検証もしてみたところ、目立った違いは現れなかったので、冷却による性質の変化は可逆的だと考えられる。
まとめ
今回の検証によって、コーヒーの産地・品種および加工方法の違いは、挽き目に影響しないことが分かった。したがってブレンドコーヒーであっても、豆を混ぜた状態で挽いてしまって問題ないことが確認できた。
また、液体窒素やドライアイスで冷した状態の豆を挽いたほうが、小さい粒になり粒度が安定することが明らかになった。
しかし冷凍庫の温度で冷やした場合には、常温より大きな粒になるという結果になった。このメカニズムについては更なる調査が必要。
現段階では、飲食店等で液体窒素やドライアイスを使って豆を冷やすというのは現実的ではないが、将来的に冷却状態のまま安定して保存し、使用する技術が現れれば、コーヒーの味の底上げになりうる。
また工業的観点から見れば、冷やすことにはコストが掛かるが、粒度が安定すればムダが減るので、より少ない豆からコーヒーが抽出できるようになり、コスト的にもメリットがあるかもしれない。
所感
正直、現場としては液体窒素とかどうでも良いので、普段遣いのレベルである冷凍庫〜常温でどうなるのかについて詳しく知りたかったです(笑)
追加の研究が出てきてないか探してみます。
それと、冷やした結果は分かりましたが、逆に常温以上に温めるとどうなるんでしょうか?
まあコーヒー豆の温度が上がると香りが飛びやすくなるというのが定説ではあるので検証するまでもないということだったのかもしれませんが、せっかくなら科学的なデータで知りたかったところです。




