ベルギーのブリュッセル自由大学で微生物学を研究するリュック・ド・ヴュイスト教授とネスレの共同研究により、水洗工程で槽内に存在する乳酸菌が、コーヒー豆の発酵に良い影響を与えていることが分かったそうです。
元記事はこちら。
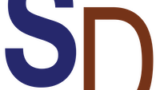
では記事の要約と所感を書きます。
記事要約
ド・ヴュイスト教授のチームは、エクアドルの試験農場で、コーヒーの収穫後の処理が、品質にどのような影響を及ぼすのかについて微生物学・代謝学のアプローチと官能評価を組み合わせた包括的な調査を実施しました。
ド・ヴュイスト教授は次のように語っています。
「発酵はとりわけ重要な工程だということが分かりました。
leuconostocs:ザワークラウトやサワードウ・ブレッドに使われるタイプの乳酸菌は発酵過程で減少し、かわりにlactobacillusという耐酸性の乳酸菌は大きく増加します。
微生物叢とコーヒーのアロマのあいだに因果関係を見出すことは簡単ではありません。
香りの原因物質には、微生物が生み出すものもあれば、コーヒー豆がもともと持っているものもあるからです。
しかし今回、微生物群とりわけ乳酸菌の重要な役割を発見することができました。
乳酸菌はフルーティな風味を生み出すとともに、彼らがつくる酸性の環境が、好ましくないニオイを生む有機体の発生を防いでいることが分かりました。
さらに、コーヒー豆への発酵関連代謝産物の蓄積があり、それがコーヒーの味わいに影響を与えています。
しかし、大部分において発酵がコーヒーの味わいに影響するメカニズムは、いまだよく分かっていません。コーヒーの水洗工程に、腸内細菌、乳酸菌、酵母、酢酸菌、糸状菌等が存在することは分かっていますが、どれが味わいに影響を与えているのかは、ほとんど謎なのです」
所感
「発酵」って、栽培や焙煎に比べると注目されにくいプロセスですが、意外と味わいに大きく影響する部分なんですよね。
しかし学問的にはほとんど中身が分かってない感じなんですね。
今回の記事も、タイトルに興味をそそられて読んでみましたけど、正直分かったような分からないような内容でした。
ぜひ産地や味わいごとの検証も見てみたいところです。
たとえばフルーティと言えばエチオピアですが、エチオピア産のコーヒーには乳酸菌が多いのかとか。
でもエチオピアって発酵方法が違っても「ナチュラルだろうがウォッシュドだろうがエチオピアはエチオピア」っていう味がしますよね。
こういった学術的なアプローチとは別に、吉祥寺のLIGHT UP COFFEEさんがバリに作った精製所で、意図的に過発酵/未発酵や発酵中にマンゴー等の果実を混ぜたロットを作ってテイスティングしたりという実験をされていて、これまた面白い取り組みだと思います。


